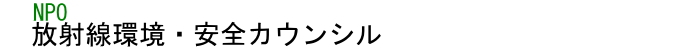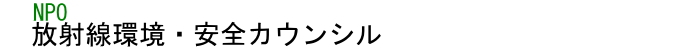「第55回 放射線環境・安全に関する研究会」印象記
|
「エンジントライボロジーへのRI・放射線利用・・・温故知新」という演題で株式会社電子応用の山本匡吾氏(元:豊田中央研究所、前:TPR株式会社)による講演が2025年1月30日(木)ナディアパーク
デザインセンタービルの名古屋市市民活動推進センター会議室で行われた。
最初にトライボロジーという用語について「摩擦、摩耗、潤滑に関わる科学と技術」というかなり広い意味を持つ造語とのことである。エンジンの開発においてRIや放射線を利用することにより、非破壊で迅速、高感度で実時間的な計測が可能になり、現象の把握やメカニズムの解析に役立ち、これまでに多くの問題解決や設計への反映が行われてきており、その内容について講演が行われた。
エンジンには多くの摺動部品があり、この摺動部の耐摩耗性の良否が耐久性に直接左右し、この摩耗を的確に計測・評価することは極めて重要である。そこで、対象部品を放射化し、運転に伴って減少する残留放射能の測定や、潤滑油中に混入する摩耗粉の放射能強度を測定することにより耐摩耗性が評価されてきた。放射化には原子炉による中性子または加速器による荷電粒子が用いられ、後者は表面層だけを放射化することから薄層放射化法と呼ばれ、ほとんどの金属に適用可能で、大型部品にも適用でき、安全性も高いことから主流となり基礎摩耗解析に幅広く貢献してきた。
また、エンジン開発において、もう一つの課題はオイル消費問題であった。オイル消費が多いとオイル補給の煩わしさやランニングコストが増加するばかりでなく、デポジットの増加、触媒機能の低下などが起こりやすい。そこで、オイルにS-35で標識された硫化オレイン酸を加え、運転中の排ガスの極微量の放射能強度を計測するシステムが開発されオイル消費量が求められた。高感度のため短期間にオイル消費特性など把握し、考えうる様々な要因が検討されオイル消費低減が実現された。トライボロジー技術の進展により、当初問題視した頃に比べて今のオイル消費は約1/10に減少し、しかもフリクションも下げることにより燃費も大幅に向上されてきた。そういえば昔は点検時にエンジンオイルの減少を気にしたものだが最近はあまり聞いたことがない。
近年シミュレーション技術は発達しているが、正確な答えを出すためにはパラメータとなる実験、試験によるデータが不可欠であり、演者らが行ったこれらの成果はデータブックとしてまとめられエンジン開発に大きく貢献してきたとのことである。
我々が普段利用している自動車が、このような技術開発の積み重ねに当たり前のように利用できていることを改めて考えさせられるとともに、日本車の品質が高いと言われる所以であろう。
なお、RI・放射線利用に関わる研究開発で43年間利用されてきたRI施設が業務の変革により2年前に廃止措置となり、今後はRI・放射線を外部機関の加速器施設などを利用する路線が主流とのこと。RI・放射線の利用に対して必要以上に敬遠される社会の風潮や規制対応の苦労があり集約化は避けられないが歴史ある施設の閉鎖は残念でならない。
|